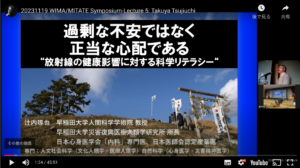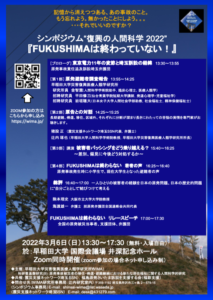2021年11月28日 早稲田大学大隈記念講堂で開催されたシンポジウムにつきまして、収録の動画がYouTubeに公開されましたのでお知らせさせていただきます。
なお、今回の企画では、若い当事者学生達の勇気ある発言に耳を傾けていただきたく存じます。様々な意見をお持ちの方がいらっしゃると思いますが、話し合いや議論のキッカケになることを望んでいます。誹謗中傷など、人を傷つける心ない対応のなきようご理解とご協力をお願いいたします。
【第1部】被災当事者学生による講演
【第2・3部】金菱清「現在大学生になる被災当事者との対話から私たちは何が学べるか」・パネルディスカッション
【第4・5部】萩原裕子「被災当事者の語りに耳を傾け学ぶことの意義」・シンポジウムのまとめ
開催概要は下記の通りです。
“復興の人間科学2021”
『福島原発事故10年の経験から学ぶー当時小学生だった若者達との対話から』
Lessons from 10 years of experience after the Fukushima nuclear accident: From the dialogue between young victims and researchers
開催日時
2021年11月28日(日曜日)10:00~18:00
開催会場
早稲田大学大隈講堂(地下1階) 小講堂(約300名)
(〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1丁目104)
※登壇者は原則全員会場にて講演。シンポジウムへ参加は無料(入場自由)
※講堂に来場できない方に対してZOOM同時配信を行います。
- 地下鉄東西線「早稲田駅」徒歩5分
- 都営バス「早稲田大学正門」徒歩1分
- 都電荒川線「早稲田」徒歩5分
- JR・西武線「高田馬場駅」徒歩20分
シンポジウムの開催に至るまでの経緯・沿革
2011年3月11日に発生した東日本大震災および原発事故から今年でちょうど10年になります。地震・津波被災者にとっては、大規模堤防建設や市町村の高台移転が完了し、復興に向けた大きな飛躍を目指す時期に入ってきました。しかし、福島第一原子力発電所事故により避難生活を余儀なくされた人々の多くは、いまだに生活基盤が確立しておらず、生活や人生における苦悩が継続しています。
2011年に「人間科学学術院としても復興に役立つ学術的支援ができないだろうか」という教授会での問題提起を機に、有志の教員によって『震災と人間科学ネットワーク』が組織され、早稲田大学人間総合研究センター(人総研)主催シンポジウムを、2012年3月および2013年3月に開催しました。
2014年10月には、早稲田大学内外の専門家による『早稲田大学災害復興医療人類学研究所(WIMA)』を早稲田大学総合研究機構内に立ち上げ、現在に至ります。
2013〜2015年の3年間は大学院人間科学研究科プロジェクト科目『災害の人間科学』、2016~2018年の3年間は人総研プロジェクト研究/大学院プロジェクト科目『復興の人間科学』、そして2020年からは科研費(B)を獲得し、このチームによる研究・調査・支援・教育活動が継続されています。
またこの間、埼玉における民間支援団体である『震災支援ネットワーク埼玉(SSN)』との密接な協働関係を築き、さらには東京災害支援ネット(とすねっと)とも協働し、被災者の方々への直接的・間接的支援や交流会活動なども継続させています。
★本チームがこれまでに行ってきたシンポジウム
2011年7月「『支援』のいまとこれから;避難所アリーナから地域へ」(主催:SSN)
2012年3月「東日本大震災と人間科学:人間科学は東日本大震災に何ができるか?」(主催:早稲田人総研)
2012年4月「震災『支援』の今とこれから:支援から協働へ」(主催:SSN)
2013年3月「(第2回)東日本大震災と人間科学:ポスト3.11の災害復興と環境問題を考える」(主催:早稲田人総研)
2013年7月「首都圏避難者の生活再建への道:大規模アンケートにみる避難者の声」(主催:SSN)
2014年11月「首都圏避難者の生活再建への道:これからの支援滑動に求められる社会的ケア」(主催:とすねっと、共催:SSN,WIMA)
2015年2月「災害復興に向けた多面的ヴィジョンの創生①:公共人類学&社会福祉学」(主催:WIMA)
2015年6月「災害復興に向けた多面的ヴィジョンの創生②:社会医学&国際保健学」(主催:WIMA)
2015年12月「災害復興に向けた多面的ヴィジョンの創生③:発達行動学&政治学」(主催:WIMA)
2016年2月「首都圏避難者の生活再建への道:予想される分断と切り捨てに対する支援のあり方」(主催SSN、共催:とすねっと、WIMA)
2017年2月「首都圏避難者の孤立を防げ:交流広場同時開催」(主催:SSN、共催:WIMA)
2018年2月「首都圏避難者の孤立を防げ:交流広場同時開催」(主催:SSN、共催:WIMA)
開催の目的・意義
原発事故による避難生活という過酷な人生体験を小学生の時期に経験した被災者は、今年で17歳~22歳となります。現在大学生となった被災当事者は、あの震災をどう受けとめ,またこの10年間をどのような社会経済状況におかれ、どのような心理状態で、どのように思考を重ね、どのように生き抜いてきたのでしょうか。
本シンポジウムの目的は、彼らのこれまでの10年の人生経験から、私たちが何を学べるのか人間科学的視座から問うものです。
本チームは、これまでに著書『ガジュマル的支援のすすめ』、『震災後に考える:東日本大震災と向き合う92の分析と提言』、『フクシマの医療人類学』、『Human Sciences of Disaster Reconstruction』や、国際誌・学会誌に数多くの成果を発信してきました。
本シンポジウムでは、心身医学・精神医学(辻内・熊野)、医療人類学(金・辻内)、発達心理学・児童福祉学(平田)、発達行動学(根ケ山)、臨床心理学(桂川・金)、教育心理学(桂川)、社会心理学(日高)、環境心理学(小島)、社会福祉学(多賀・増田・岩垣・猪股)、地域福祉学(増田)、精神保健福祉学(岩垣)、公衆衛生学(扇原・日高・岩垣)、社会学(多賀・辻内)、文化人類学(金・辻内)、法学・政治学(猪股)といったトランス・サイエンス(学際的・学融的)の観点から、未来を担う若者達の語りを傾聴し、対話を重ねることに意義があります。
本チームがこれまで10年間に行ってきたシンポジウムでは、「今被災者にとって何が問題なのか?被災者をいかに支援すべきか?」というテーマを中心に、被災当事者の方たちと専門家が対等な位置関係で互いに学び合う機会を作ってきました。中でも、本シンポジウムの特記すべき点は、震災当時小学生であった若者の経験と考えから学ぼうとする新しい取り組みにあります。
プログラム
<はじめのご挨拶>10:00~10:10
- 早稲田大学人間総合研究センター長(扇原)(約3分)
- シンポジウムの企画趣旨(大会実行委員長:平田)(約7分)
<第1部>(合計170分、10:10~13:00)
① 「原発事故10年の経験」:原発事故による避難経験がある、震災当時小学生だった大学生5名による講演。双葉町・福島市・郡山市・いわき市出身。(各20分)
② 「被災当事者学生へのインタビューを通して学んだこと」:上記当事者5名それぞれに対して事前にインタビューを行った早稲田大学人間科学部学生による調査結果と考察の発表。(各8分)
③ 本シンポジウム企画教員5名(熊野・小島・桂川・増田・日高)によるコメント。(各5分)
・・・休憩3人目と4人目の間(5分、11:50~11:55)
・・・昼休み食事休憩(60分)
<第2部>(合計60分、14:00~15:00)
基調講演:『被災当時小学生だった若者との対話から私たちは何が学べるか』
金菱清(関西学院大学社会学部教授、災害社会学・環境社会学)
[講演者紹介]
金菱清先生は、2011年東日本大震災発生当時から、東北学院大学教養学部地域構想学科にて、被災当事者を含む学生たちと共に「東北学院大学・震災の記録プロジェクト」を続けてこられた。
著作『3.11慟哭の記録:71人が体験した大津波・原発・巨大地震』(新曜社)は、第9回 「出版梓会新聞社学芸文化賞」を受賞され、その後も、『呼び覚まされる霊性の震災学:3.11生と死のはざまで』(2012)、『悲愛:あの日のあなたへ手紙をつづる』(2017)、『3.11霊性に抱かれて:魂と命の活かされ方』(2018)、『私の夢まで会いに来てくれた:3.11亡き人とのそれから』(2018)、『震災と行方不明:曖昧な喪失と受容の物語』(2020)、といった金菱ゼミナールの学生たちとの対話を通じて作成された、学生たちのフィールドワークやインタビュー調査を含めた著作を次々と世に出してきた。
大規模授業においても、被災経験のない学生たちに被災体験を想像させ理解を深める新たな教育法を実践されてきています。2020年より、関西学院大学社会学部教授。
本シンポジウムでは、被災当事者の学生たちに学ぶことを中心テーマに置いており、まさにこのテーマの実践を続けてこられています。
(金菱清先生ウェブサイトはこちら)
・・・休憩(10分)
<第3部>(合計90分、15:10~16:40)
パネルディスカッション:第1部発表の被災当事者学生8名、第2部の基調講演者(金菱)、第4部講演者1名(萩原)とのクロストーク
① テーマA:原発事故後10年の経験の意味・意義を考える
② テーマB:ポスト3.11およびポストコロナの日本社会の在り方を考える
③ テーマC:若者達による日本社会・国際社会への提言
・・・休憩(10分)
<第4部>(合計30~40分、16:50~17:30)
講演:『被災当事者の語りに耳を傾け学ぶことの意義』
(震災支援ネットワーク埼玉心理相談チーム代表、萩原裕子)
<第5部>(合計20分、17:30~17:50)
シンポジウム全体へのコメントとまとめ
根ケ山・・・早稲田チーム顧問として(10分)
猪股・・・SSNチーム代表として(10分)
<おわりの挨拶>(合計10分、17:50~18:00)
大会長(辻内)
予定する主な講演者・発表者
| 氏名 | 所属機関名 | 職名 |
|---|---|---|
| 【WIMA早稲田大学学内発表者】 扇原 淳 小島 隆矢 桂川 泰典 熊野 宏昭 根ケ山 光一 | 早稲田大学人間科学学術院 早稲田大学人間科学学術院 早稲田大学人間科学学術院 早稲田大学人間科学学術院 早稲田大学人間科学学術院 | 教授(社会医学・公衆衛生学) 教授(建築学・環境心理学) 准教授(臨床心理学・学校カウンセリング) 教授(行動医学、臨床心理学) 名誉教授(発達行動学) |
| 【シンポジウム招聘講演者】 金菱 清 萩原 裕子 | 関西学院大学社会学部 震災支援ネットワーク埼玉(SSN)心理相談チーム代表 | 教授(災害社会学・環境社会学) 文教大学人間科学部非常勤講師(臨床心理士) |
| 【WIMA学外発表者】 多賀 務 増田 和高 日高 友郎 岩垣 穂大 猪股 正 | 東京都健康長寿医療センター研究所 武庫川女子大学文学部 福島県立医科大学医学部 日本女子大学人間社会学部 震災支援ネットワーク埼玉(SSN) | 研究員(社会学・老年学) 准教授(社会福祉学・地域福祉学) 講師(衛生学・社会心理学) 助教(社会福祉士・精神保健福祉士) 代表(弁護士) |
| 【WIMA招聘研究員】 菊池 靖 リチャード F.モリーカ 安田常宏 仲佐 保 関谷 雄一 土田 マリサ 北村 浩 土屋 葉子 猪股 正 桂川 秀嗣 中川 博之 萩原 裕子 愛甲 裕 佐藤 純俊 | 早稲田大学アジア太平洋研究科 ハーバード大学,難民トラウマ研究所 マサチューセッツ総合病院、 シェア=国際保健協力市民の会 東京大学大学院総合文化研究科 小石川インターナショナルクリニック 公益財団法人政治経済研究所 早稲田大学人間総合研究センター 震災支援ネットワーク埼玉(SSN) 東邦大学理学部 震災支援ネットワーク埼玉(SSN) 震災支援ネットワーク埼玉(SSN) 震災支援ネットワーク埼玉(SSN) NPO法人全国福島県人友の会 | 名誉教授(開発人類学)、WIMA顧問 教授、所長、医師 心臓核医学、医師 共同代表(医師) 教授(文化人類学・開発人類学) 医師 主任研究員(政治学) 招聘研究員、翻訳者(公衆衛生学) 代表、弁護士 名誉教授(原子核物理学) 司法書士 臨床心理士、公認心理師 ITエンジニア 代表(社会福祉主事) |
主催
- 早稲田大学人間総合研究センター
- 早稲田大学災害復興医療人類学研究所(WIMA)
- 科研費補助金(基盤研究B)『原発事故被災者の移住・帰還・避難継続における新たな居住福祉に関する人間科学的研究』
共催
- 震災支援ネットワーク埼玉(SSN)
開催実施者
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 【大会長】 辻内 琢也 | 早稲田大学人間科学学術院 教授 早稲田大学災害復興医療人類学研究所 所長 震災支援ネットワーク埼玉(SSN)副代表 |
| 【実行委員長】 平田 修三 | 仙台青葉学院短期大学 講師 |
| 【事務局長】 金 智慧 | 早稲田大学人間科学学術院 助手 |